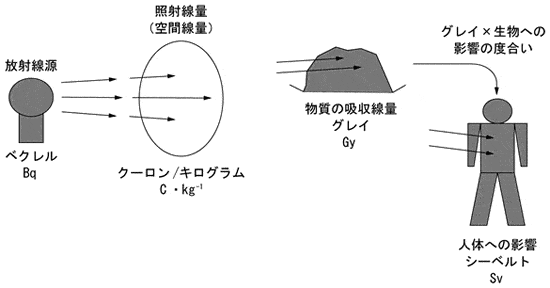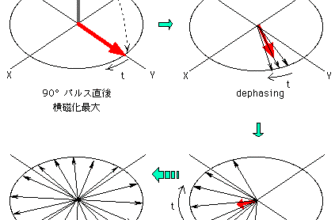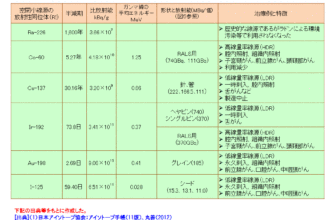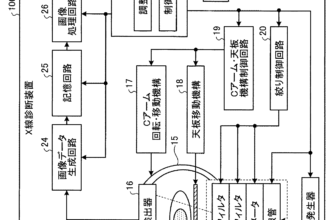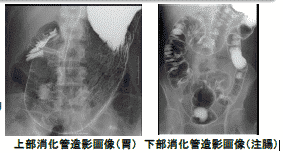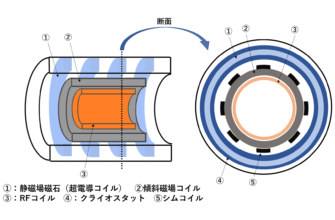放射線量の計測では、この3つの物理量は名称が違っていて違う内容を計測していることは想像できます。
でも、この3つの定義を調べてみると内容がわかりにくい!!
この記事を書こうと考え、勉強し直してみても差がわかりにくいし、ややこしい。というのが正直な感想です。
そこで、今回はこの3つの物理量の違いを1つずつまとめてみたいと思います。
なるべく簡単にできるよう頑張りたいと思います。
スポンサーリンク
照射線量とは?
照射線量(X)はdQというエネルギーの単位からdmという質量で割った値になります。
なので、最初に式で表してしまうと以下のようになります。
単位は 【C/kg】 クーロン・パー・キログラムと読み、クーロンというエネルギーを質量で割った値であることを意味しています。
では、ここでいう dQ とは何のエネルギーであり、dm とはどんな物質の質量となるのでしょうか。
これにはまず、照射線量で定義されている物質とは何かを知る必要があります。
ただ、その答えはとても簡単で空気です。
照射線量を測定する場合、水や油、またはアクリルなどの化学物質では測定を基本的には行いません。(ただ、質量dmなる空気の領域さえ確保できれば空気以外の物質の任意場でも許されているらしいですが・・・。その時は、そこに空気が存在したという想定で行うらしいです。)
照射線量を測定する場合、その測定する場所は空気中であり、その空気の質量が上の式に含まれる dm の正体となります。
なので、照射線量の定義文にも質量 dm の空気とはっきり明記されています。
個人的には、空気というのがあまりにも当たり前に存在し、重さがあると考える機会のほうが少なく、イメージしずらかったのですが、放射線というのも認識できないほと小さいものなのでしょうがないと思い納得することにしました。
さて、dmが空気の質量を表していることを理解したら、今度は dQ が何のエネルギーを表しているのか?ということになるのですが、これは少し複雑です。
ただ、定義文を借りるのであれば、
質量 dm の空気領域内で光子によって生成された電子・正イオン対が完全に停止するまでに空気中で発生する一方の符号のイオンの全電荷の絶対値。
と、なるのですが・・・わかりにくいです!!
そこで、ここでは、簡単に照射された光子(X線やγ線)が『ここで照射線量を測定しますよ!』と勝手に決めた範囲(空気中)で発生した電子と陽電子の全電荷量と考えてみることにします。
もっと簡単に考えるのであれば、決めた範囲(ただし空気中だけ)で光子によって起こった全ての電気量でいいかもしれません。
ただ、ここで注意があります。
決まった領域内で起こった全電荷量を測定し、測れた値が照射線量なのか・・・というと違うからです。
照射線量を測定する上で、決めた空気領域内で起こった電子・陽電子の全てを測定してはダメとされています。
では、どんなものが測定対象となり、どんなものが測定対象とはならないのか。
これには、細かく、そして少しだけ複雑にしっかりとした定義づけがされており、以下のようになります。
・測定対象に含まれるもの
➀光子(X線やγ線)によって領域内部で発生した電子対
➁領域内部で発生した二次電子
(二次電子による電離の寄与は、領域外の電子が静止するまで含む)
・測定対象に含まれないもの
➀領域内で新たに発生した制動放射
➁二次電子よって起こった制動放射がさらに起こった電子対
➂電荷領域外で発生した二次電子の寄与
最後に最近ではあまり使用されていない旧単位であるレントゲン 【R】 との関係についても触れたいと思います。
・1 [R] = 2.58 ✖ 10⁻⁴ [C/kg]
・1 [C/kg] = 3876 [R]
です。
教科書的には、まだレントゲン 【R】 という単位はなくなり切っていないとのことなので、参考までに載せてみました。
スポンサーリンク
カーマとは?
次はカーマについて細かく見ていきたいと思います。
カーマ(K)も照射線量と似ており、dEtrというエネルギーを質量 dm で割った値です。
なので、式で表すと以下のようになります。
単位は【J/kg】ジュール・パー・キログラムと読みます。ジュールは熱量などのエネルギーを指す単位なので、エネルギーを何かの質量で割った値であることを意味します。
照射線量では、C(クーロン)だったので単位の上でも少し違いがあります。 また、カーマ単位には、別の呼び方もあります。 それが、グレイ【Gy】です。
最近は、放射線の量を示す単位として知られているので、知っている方も多いかもしれませんが、このカーマにもGy(グレイ)が使用されています。
【J/kg】と【Gy】のどっちを使えばいいのかという疑問も生まれるかもしれませんが、どちらも一緒です。 【J/kg】=【Gy】なので、使用する場で統一して使用されているほうを使用すれば良いかと思われます。
ただ、この後にも説明しますが、実は吸収線量もグレイ【Gy】という単位が使用されています。
そこで、吸収線量とカーマでは、厳密には違う意味を示す単位であるため、混乱しないようにする処置が必要です。
カーマでGy(グレイ)という単位を使用する場合は、カーマグレイと俗称的に使用されることがあるので、頭の片隅程度には覚えておくと良いでしょう。
では、単位から話を戻し、照射線量の時と同様、dE とは何のエネルギーを意味し、dm とは何の質量を示しているのかまとめていきたいと思います。
これには、まず何の物質の質量を表しているのかである dm から説明していきたいと思います。
が、実は、カーマでは定義となる物質は存在しません。
どんな物質であっても良いとされています。なので、全ての物質としか定義の中にもありません。
照射線量の時のように空気といった限定はないので、水でも脂肪でも照射線量に合わせて空気でも構わなく、任意とされています。(都合のよいもで測定してくださいと取れなくもないです。)
ただ、どんな物質中でも良いとされる値であるため、その値を見ただけではどんな物質を使用し測定された値なのかというのが伝わりにくい単位でもあります。
そこで、空気の場合は空気カーマと物質名を明記したうえで値を表示するのが一般的です。
よって、 dm とは何の質量なのかという回答には、どんな物質でもいいから決まった領域を設定し、その範囲でのその物質の質量ということになります。
では、dE とは何かという話に移っていきたいと思います。
カーマでは何のエネルギーを示すのかについては、まずは定義から確認したいと思います。
定義の中で、dE とは質量 dm なる物質中で非荷電粒子により生じた全ての荷電粒子の初期運動エネルギーの総和とされています。
やっぱり、少ない文章で色々と盛り込まれるのでわかりにくいです。
そこで、一つずつ確認したいと思います。
照射線量の時の光子とは違い、非荷電粒子とあります。
何が違うのかというと、ほとんどかわりません。なぜなら、光子も非荷電粒子の一種だからです。
ですが、あえて非荷電粒子と表記されているのにも当然ながら理由があります。それは、「光子(X線やγ線)に追加して中性子線も測定対象に加えてね」ということです。
なので、カーマでは、X線、γ線、中性子線に適応される単位となります。
さて、ここから少し難しくなります。
荷電粒子の運動エネルギーとは何かです。
そもそも、X線やγ線、中性子線が照射されると、励起や電離を起こします。
その時に、生じるのが荷電粒子であり、電子や陽電子が代表的です。
ただ、このように生じる電子や陽電子は、非荷電粒子が照射される前では物質中で留まって存在しているか、元からは存在せず、X線やγ線が消滅するときに代わりに発生する(電子対生成)かになります。
なので、元々は動いていないまたは存在していないものとなります。
ですが、非荷電粒子が照射されることで、これらの電子や陽電子は動くためのエネルギーを受け取り、元々、住んでいた原子中を飛び出すことになります。
この、飛び足すときの最初のエネルギーが荷電粒子の初期の運動エネルギーということになります。
カーマでは全ての荷電粒子の初期運動エネルギーの総和を物質の質量で割った値なので、非荷電粒子が照射されて決められた物質中の範囲の中で動き出した荷電粒子のエネルギーを測定し、一つのエネルギーとしてみましょうということになります。
ただ、照射線量の時と同様にカーマでも測定に含むエネルギーと測定対象に含まれないエネルギーがありますので、以下にまとめたいと思います。
・測定対象に含む
➀非荷電粒子が照射されて物質中で生じた二次荷電粒子
➁領域内で発生した二次荷電粒子が領域外に出て領域外の領域に落とすエネルギー
➂制動放射によって領域外に落とす全てのエネルギー
・測定対象に含まない
➀領域外で発生して領域内に入ってきた二次荷電粒子のエネルギー
照射された非荷電粒子が決めらた領域に到達するまでに発生させた荷電粒子のエネルギーは含みません。
ちなみに、領域内で発生した二次荷電粒子が発生するときに新たなX線を生じる場合があります。(制動放射)その場合、二次荷電粒子の初期エネルギーから制動放射によって落とされたエネルギーを減じたものを衝突カーマと呼びます。
吸収線量とは?
では、吸収線量についてまとめていきたいと思います。
吸収線量も上の2つ同様に、エネルギー dε を dm で割り算をした値であり、以下のように示すことができます。
単位は【J/kg】であり、カーマの時同様【Gy】とも表記されます。
では、上の二つ同様にエネルギーの内容と物質の内容を説明していきたいと思います。
まず、吸収線量を知るうえで頭に入れておくことは、定義付けが最も大雑把だということです。
これまで、照射線量、カーマとまとめていきましたが、どちらも測定に含むエネルギーの内容や物質の種類に制限がありました。
しかし、吸収線量は違います。
どんな放射線(電離放射線)の種類であっても、どんな物質であって良いということになります。
なので、早速、吸収線量を求める際にどんなエネルギーを測定する必要があるのかについてまとめてみたいと思います。
測定するエネルギーの定義を確認すると、質量 dm の物質中で電離放射線によって付与される平均エネルギーとなります。
ここで、注意するべき点は、使用されるエネルギーが平均値であることです。
照射線量、カーマのそれぞれは物質中で起こったエネルギーの総和でしたが、吸収線量はエネルギーの総和を個数で割った平均エネルギーになります。
しかし、ここで問題があります。
エネルギーの総和は測定された値を用いれば良いということは想像できますが、個数とはどうやって求めるのでしょうか。
量を求める対象が目に見えないような放射線のため見て数えることはできません。
そこで、使用するのがW値という値になります。
W値とは、1個のイオン対(電子・陽電子対)を作るのに必要な平均エネルギーのことです。
式で表すと、
E:エネルギー
N:イオン対数
入射荷電粒子により生じた制動放射線や二次電子などにより生成されたイオン対もNに含まれる。
なのですが、また結局、個数が必要じゃん。
と思われるかもしれませんが、測定対象が空気の場合、必要がありません。
なぜなら、もう最初から決まったW値があるからです。
空気の場合、1個のイオン対を作るの必要なエネルギー(W値)というのは、33.97[eV]を使用しようというのが一般的に決まっています。
なので、ある領域で生じたエネルギーの総和をW値で割り算してあげることで、その時に生じたイオン対数がわかることになります。
結果として、個数が分かれば平均エネルギーも求めることが可能となるのです。
ただ、ここでW値によって求められるイオン対数はあくまで期待値(理論上の値)であることは忘れてはいけません。
実際には、統計的に誤差が生じるので測定を何度も何度も繰り返し行い、その平均値を用いることが理想的です。
ということで、吸収線量を測定する際にも測定対象に含むもの含まないものをおさらいしたいとおもいます。
・測定対象に含む
➀電離放射線によって領域内で生じたエネルギー付与の全て
➁領域外で発生した二次電子
➂制動放射によって領域内で発生した二次電子などによる領域内におけるすべてのエネルギー付与
・測定対象に含まない
➀制動放射
制動放射は領域内で新たな電離を起こさない限り、エネルギーを付与することはありません。自ずと測定対象から外れることになります。といっても電離を起こさない限り、放射線計測の前提として測定することはできませんが・・・。
まとめ表
ここまで、照射線量、カーマ、吸収線量の3つについてまとめてきましたが、読んだいるときはそれぞれの意味を理解できたかもしれませんが、違いと言われるとどこがどう違っていたのか混乱しそうです。
そこで、表にまとめて、それぞれを確認してみたいと思います。 参考まで見ていただければ幸いです。
| 照射線量 | カーマ | 吸収線量 | |
|---|---|---|---|
| 測定対象 | 光子 | 非荷電粒子線(X線・γ線) | 全ての電離放射線 |
| 物質 | 空気 | 全ての物質 | 全ての物質 |
| 測定対象に含む | ➀光子よって領域内部で発生した電子対 ➁領域内部で発生した二次電子 |
➀物質中で生じた二次荷電粒子 ➁領域内で発生した二次荷電粒子が領域外にでて領域に落とすエネルギー ➂制動放射によって領域外に落とす全てのエネルギー |
➀電離放射線によって生じたエネルギー付与 ➁領域外で発生した二次電子 ➂制動放射によって領域内で発生した二次電子などによる全てのエネルギー付与 |
| 測定対象に含まない | ➀領域内で新たに発生した制動放射 ➁二次電子によって起こった制動放射がさらに起こした電子対 ➂領域外で発生した二次電子の寄与 |
➀領域外で発生して領域内に入ってきた二次荷電粒子エネルギー | 制動放射 |