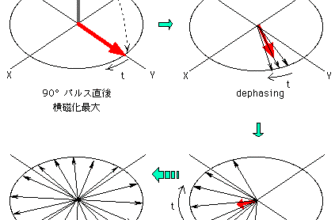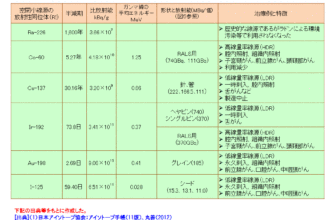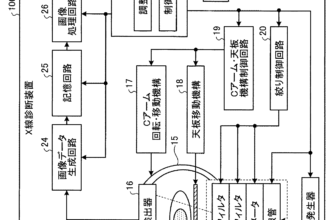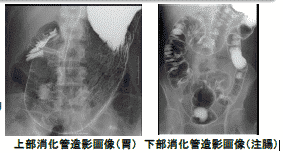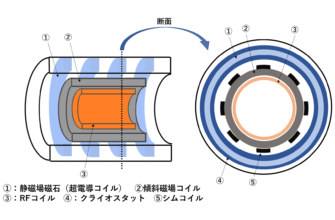MRIを勉強するうえで、絶対に避けられないTRとは?
結論からいうと、
TR(time to repeat)のことで、繰り返してRFパルスを使用するときに使う用語で、RFパルスを照射するごとの時間の長さを表しています。
具体的にいうと、縦磁化を横磁化にするために90°パルスを使いますが、実際の検査では、この90°パルスを繰り返して使うことになります。90°パルス照射から次の90°パルス照射までの時間がTR(繰り返し時間)と呼ばれているのです。
では、このTRがどのような影響を及ぼすのか?
今回は、そのことをじっくりまとめてみたいと思います。
スポンサーリンク
例えば・・・
緩和時間の異なる、二つの組織AとBがあるとします。
組織Aのほうが縦緩和、横緩和時間ともに短く、Bは長い組織です。(Aのほうが、RFパルスを切った後に横磁化から縦磁化に戻るの速く、陽子の位相もバラバラになりやすいので、横磁化の消失が速いということです。)
この二つの組織に90°RFパルスを送り、ある時間を待ちます。そして、2回目の90°パルスを送ります。(1回目から2回目までの時間がTR(繰り返し時間)です。)
すると、どうなるのか?
それは、2回目までの時間、つまりTRが長いときと短いときでは、結果が違ってくるのです。
まず、長いとき(TR long)にはどうなるのか。
それは、1回目と2回目までの時間が長いために、この時間の間に組織AとBともに縦磁化を回復させてしまいます。
すると、2回目のRFパルスを照射するときには、組織AもBも回復しきっているので、縦磁化の大きさが同じくらいになっています。
この段階で、もう一度90°パルスを照射して横磁化ベクトルを生み出し、信号を受信しても、その信号が組織Aからのものなのか組織Bからなのか区別することは困難です。
図に表すと、下のような感じになります。
一方、TRが短い(TR short)ときにはどうなるのか?
2回目のRFパルスをさっきよりも早い段階で送ります。その時、組織Aは組織Bよりも大きな縦磁化の回復があります。組織Bは回復が不十分だと、思ってもらってもいいです。
ここで、2回目の90°パルスが縦磁化を90°傾けると、組織Aの横磁化ベクトルは組織Bの横磁化ベクトルよりも大きくなるのです。すると、組織Aのほうが、強い信号をアンテナに送信することができるようになります。
つまり、組織Aから出されれる信号が際立っているのです。
そうすることで、組織Aと組織Bと区別することができるようになります。
ここで、重要なのは、90°パルスを2回送っているということと、2回目の90°パルスを送るまでに長い時間待ってしまうと、二つの組織を区別できなくなってしまうということです。
TRの長さは二つの組織を区別するためにとても重要で、長いときには組織AとBの緩和時間の違いを利用できないことになってしまいます。
スポンサーリンク
TRが画像に与える影響とは?-T₁強調画像-
長いTRは、二つの組織からは同じような信号が得られ、MR画像上も同じように見えて、区別することができません。
しかし、短いTRを使うと、組織の緩和時間(T₁)の違いによって二つの組織間の信号強度が異なり、画像でも区別することができるようになります。
この緩和時間(T₁)の違いを表している画像をT₁強調画像(T1WI:T₁-weighted images)と呼んでいます。
つまり、画像中の組織間の信号強度の違い(組織コントラスト)は、主にそれらの組織のT₁の違いによって起こっていることになるのです。
ただ、組織コントラストに影響を与えるパラメーターは常に複数あることは忘れるわけにはいきません。
あくまで、緩和時間(T₁)は影響与えるパラメーターの一つです。
この差を利用して、T₁強調画像を作る。
短いTR、長いTRとは?
ちなみに、さっきからTRが長いやら短いやら言っていますが、実際どの程度から長く、短いのでしょうか?
それは、
500msecよりも小さいTRは短い。
1500msecよりも大きいTRは長い。
と考えられています。
TRが非常に長い時には・・・プロトン密度強調画像
上の説明でいくと、TRが長いと、二つの組織の信号強度は同じになり、組織間のコントラストがつかないことになります。が、実際の画像上では、そうならないことのほうが多く、信号強度には差があります。
それは、なぜか?
この原因には、プロトン密度が関係しています。
プロトンとは陽子のことですが、MRI検査では、陽子がないところには信号はなく、陽子の多いところには”多く”の信号があります。
ここで、忘れてはならないのは、MR画像の信号強度に影響を与える因子は一つではないということです。
TRを非常に長くすると緩和時間(T₁)は組織コントラストに影響を与えなくなりますが、異なる組織であれば、組織含まれる陽子の量(プロトン密度)も違いがあるかもしれません。このプロトン密度の差が組織間のコントラストとなって、画像上に表示されることになります。
そして、プロトン密度の差を画像化したものをプロトン密度強調画像といいます。